いま、BCP対策は「費用」ではなく「投資」
地震・台風・感染症・サイバー攻撃など、企業を取り巻くリスクは年々多様化しています。
「いざというときに、事業を止めずに動かす」。
その仕組みを備えているかどうかが、企業の生存率を左右する時代です。
しかし、BCP(事業継続計画)の構築や訓練、設備整備には多くのコストがかかります。
限られた予算の中でどこまで実現できるのか――そこに大きな悩みを抱える企業は少なくありません。
そんな企業を後押しするのが、東京都の「BCP実践促進助成金」制度です。
制度を上手に活用すれば、初期費用を抑えつつ、実効性の高いBCP体制を整えることができます。
BCPとは何か?
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は、自然災害、火災、感染症拡大、テロ攻撃などの緊急事態が発生した際に、事業活動を継続し、または早期復旧を図るための計画です。
単なる防災マニュアルではなく、「どの業務を優先的に守るのか」「誰がどのように行動するのか」「社員・取引先・顧客とどう連携するのか」を具体的に定めた、経営レベルの戦略です。
その実効性を高める鍵が、平時から“動く”仕組みを整えておくことです。
TeamsやSlackなど、日常業務に組み込まれたツールで災害時にも即座に動ける体制づくりが重要です。
東京都の「BCP実践促進助成金」とは?
BCP対策には、設備投資、システム導入、専門家相談費用など、多くの経費が発生します。
補助金・助成金を活用することで、これらの費用負担を大幅に軽減し、より充実したBCP対策を実現できるのは大きなメリットです。
また、申請プロセスを通じて自社のリスク分析や継続戦略を深く検討するため、BCP策定の質も向上します。
さらに、公的支援を受けることで、取引先や金融機関からの信頼度向上も期待できます。
そうした背景の中で注目を集めているのが、東京都が実施する「BCP実践促進助成金」です。
公益財団法人 東京都中小企業振興公社が運営する本制度は、中小企業・小規模事業者が「実効性のあるBCP対策」を進めるための費用をサポートするもので、防災力と事業継続力の両面を強化できる支援制度です。
助成率:中小企業者:1/2以内/小規模企業者:2/3以内
助成限度額:上限1,500万円(うち基幹システムクラウド化は上限450万円)
下限額:10万円
申請タイプ:単独型(1事業者)・連携型(複数事業者)
実施主体 公益財団法人:東京都中小企業振興公社
対象エリア:単独型(東京都内)、連携型(1都6県+山梨(代表者は東京都内))
申請方法:JGrants電子申請システム
※2025年11月17日時点の情報をもとに作成しています。
制度内容は年度ごとに更新されるため、最新情報の確認が必須です。
詳細は公式サイト(東京都中小企業振興公社):
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html
をご確認ください。
助成対象経費の中に「安否確認システム」
この制度では、BCP実践に必要な多様な経費が対象となっています。
自家発電装置・蓄電池
感染症対策物品・従業員備蓄品
データバックアップ用サーバーやクラウドサービス
安否確認システム(通信・情報共有体制の強化)
耐震診断や防災設備の導入
つまり、否確認サービス「アンピー」のようなシステムも、「災害時の初動対応を支える通信インフラ強化」として、助成対象となるケースがあります。
他の制度との併用も可能
東京都の制度に加え、国の支援制度も活用可能です。
➀事業継続力強化計画(経済産業省)
→ 税制優遇・低利融資・補助金加点
②日本政策金融公庫「BCP資金」
→ BCP策定企業への低金利融資
③地方自治体の独自助成制度
→ 例:江戸川区「BCP策定助成金」(上限20万円)
補助金と融資を組み合わせることで、より大規模な防災投資も無理なく実現できます。
まとめ
BCP対策は「備える」だけでなく、「動ける」ことが重要です。
安否確認サービス「アンピー」を活用すれば、
日常の延長で災害時も即座に社員の安否を確認し、的確な判断ができます。
助成金をうまく活用することで、
「コスト」ではなく「投資」としてのBCP対策を実現しましょう。
この記事は2025年11月17日時点の内容をもとにまとめています。
制度は更新される可能性があるため、最新情報は公式サイトにてご確認ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html

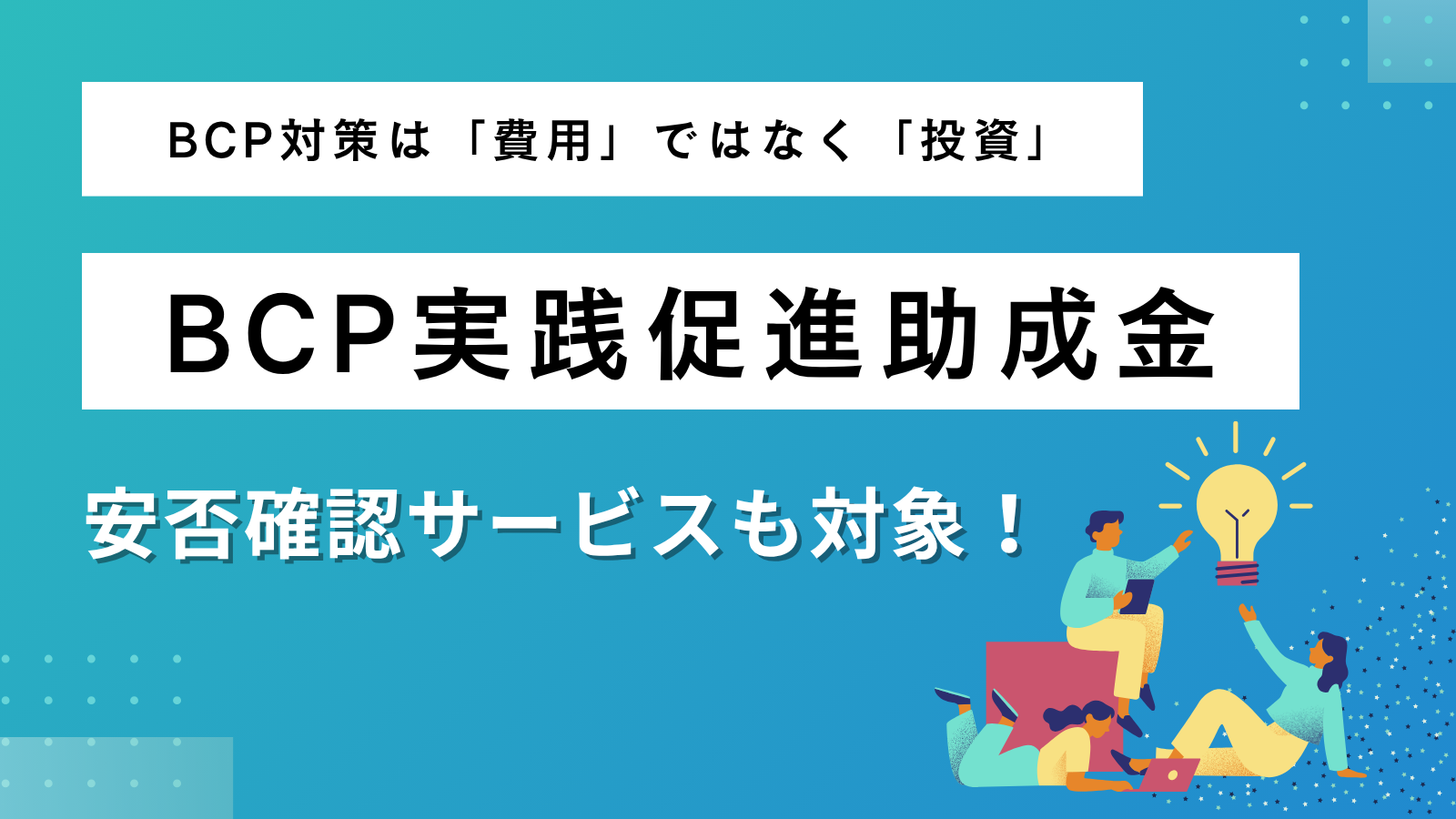


コメント